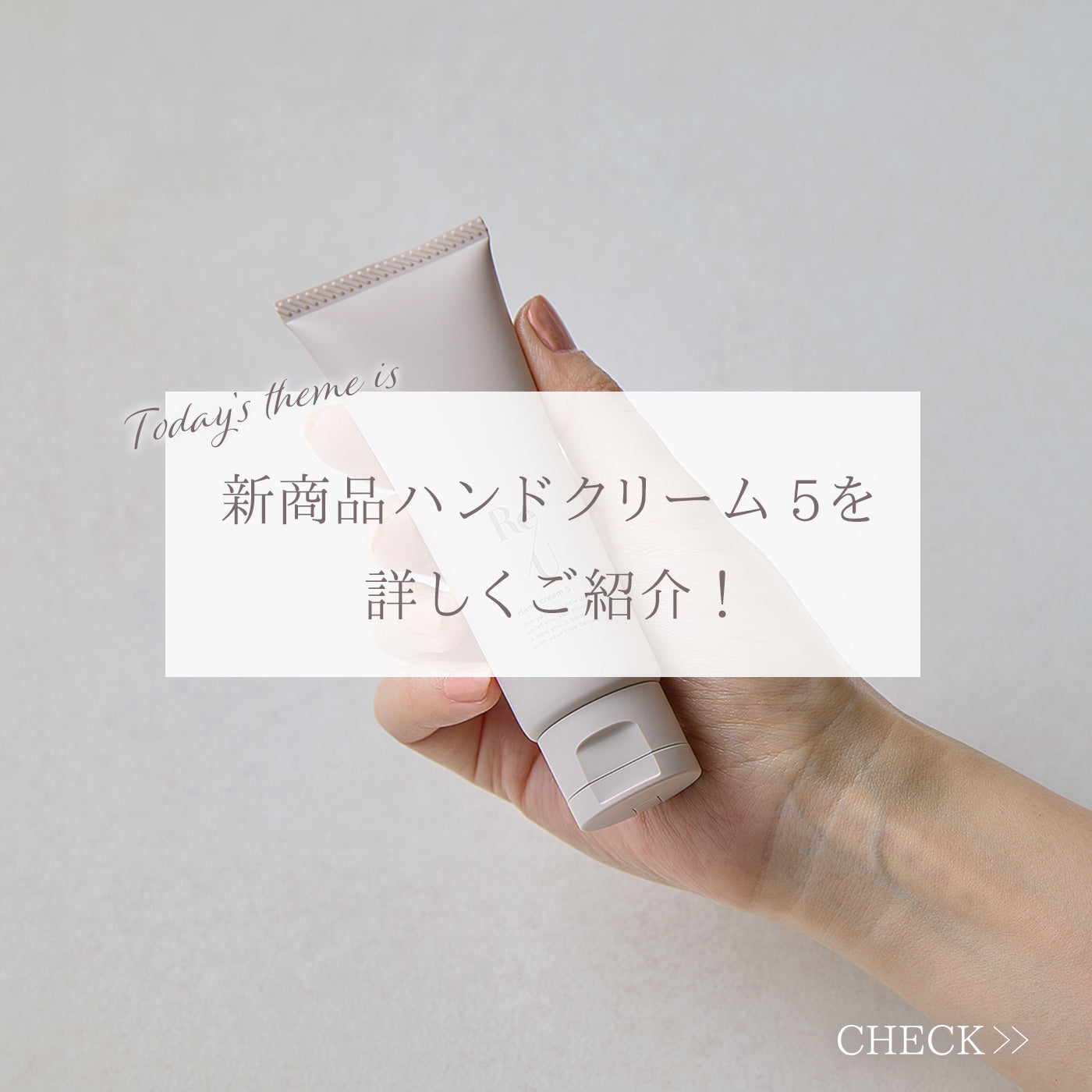骨盤底筋は、姿勢や尿もれに関わる重要な筋肉。前回のコラムでは、その働きと、機能が低下すると起こるトラブルについて解説しました。
今回は、実際に骨盤底筋をどのように鍛えるべきかについて、MTXスポーツ・関節クリニックの理学療法士、猿田奈央さんにお話を伺いました。
トレーニングの詳細については、MTXスポーツ・関節クリニックで実施している骨盤底筋トレーニングに基づき、2回にわたって解説いたします。
■MTXスポーツ・関節クリニックとは
猿田さん:MTXスポーツ・関節クリニックは、完全自費診療の整形外科クリニックです。再生医療に注力し、トップアスリートからスポーツ愛好家、痛みや機能障害を抱える方やスポーツ未経験者まで幅広く対応しています。診察からリハビリまで一貫した根本治療を目指し、専門スタッフがサポートします。

プロが指導するトレーニングと自己流の違い
猿田さん:ここからは、プロによる正しく効率的なトレーニング法と、自己流トレーニングによる体への負担とリスクについて詳しく解説いたします。
1. クリニックで行う骨盤底筋トレーニングの特徴とメリット
猿田さん:トレーニングをするときに「本当に正しくできているのか?」と不安になりませんか?当院ではエコーを使い、自分の骨盤底筋の動きを画面で確認できます。これにより、実際の動きが分かり、間違った力の入れ方を防げるのが大きなメリットです。
さらに、理学療法士が一人ひとりの状態に合わせたトレーニング方法を指導するので、効率よく鍛えることができます。
2. 自己流トレーニングの危険性
猿田さん:最近は雑誌やメディアでも「骨盤底筋トレーニング」や「膣トレ」が紹介されていますが、自己流で行うことのリスクについてご存知でしょうか?
骨盤底筋ではなく、誤ってお腹やお尻の筋肉を使い、骨盤底筋にアプローチできていないことがあります。「しっかり力を入れよう」と頑張りすぎると、逆に内臓を押し下げてしまうことも。
その結果、腰や股関節に負担がかかり、かえってトラブルを引き起こすことがあるので注意が必要ですがご安心ください。「正しいトレーニング方法」を身につければ、年齢やスポーツ経験問わず、骨盤底筋を無理なく鍛えることができます。
以上のことから、自己流のトレーニングとプロによる指導のトレーニングには大きな違いがあります。適切な骨盤底筋トレーニングはシンプルで、一見地味に見えることがあります。
ですが、体の基礎を支える重要なトレーニングであるため、実際に当院で行っているエコーを使用した骨盤底筋の使い方や意識の持ち方、指導の様子をお見せしながら解説していきます。
■骨盤底筋の正しい使い方
猿田さん:トレーニングを実践する前に、エコーによる骨盤底筋の状態を見ていきます。
骨盤底筋を動かせる範囲(上げる・下げる動き)、筋肉の素早い動き/持久力がどのくらいあるのかを把握します。トレーニング開始時点の機能には個人差があり、それぞれのスタート地点からトレーニングを開始します。

STEP1 骨盤底筋を「感じる」ことから
猿田さん:まずは、「骨盤底筋をちゃんと動かせているか」を確認しましょう。
このステップでは、リラックスしながら、骨盤底筋を意識しやすくする準備運動の段階です。
骨盤底筋群を意識して力を入れること(収縮・引き上げ)が出来るか、骨盤底の柔軟性が有るかをチェック。
この段階では
・感覚トレーニング
・胸郭や股関節の柔軟性と可動域(無理なく広く動かせるかどうか)
・呼吸の練習
などを行います。

STEP2 正しい動きを身につける
猿田さん:次に、骨盤底筋を正しく使えるように練習します。エコーを使って動きを確認したり、日常の動作の中で意識する練習をしていきます。
・エコーで自分の動きを確認(力の入れ方が正しいかチェック)
・エコーなしでもできる感覚を身につける(「この感覚が正解◎」を体で覚える)
ご自身で意識できるまで繰り返し練習をします。

骨盤底筋を意識できるようになるとリズムよく収縮できるようになる
ここまでのステップがスムーズにできるようになれば、次はいよいよ本格的なトレーニングへ進みます。骨盤底筋の「瞬発力(素早く収縮する力)」と「持久力(長く支える力)」を高め、より安定した動きができるようになることを目指します。
最終的には、日常生活の動作はもちろん、スクワットやジャンプなどの運動、さらにはヨガやピラティス、軽いスポーツの場面でも骨盤底筋を適切に使えるようになります。
まずは、日常の中で少しずつ骨盤底筋を意識することが大切です。
当院では、一人ひとりが「意識しやすい方法」を見つけられるように指導していきますので、ご安心ください。
例えば、
・「膣を優しく締めて引き上げるイメージ」
・「椅子に敷いたティッシュペーパーを会陰部でつまみ上げるイメージ」
など、具体的なイメージを使うと、より分かりやすくなります。
次回は、実際のトレーニングをお見せしながら解説いたしますのでお楽しみに。
\今回お話を伺ったのは/