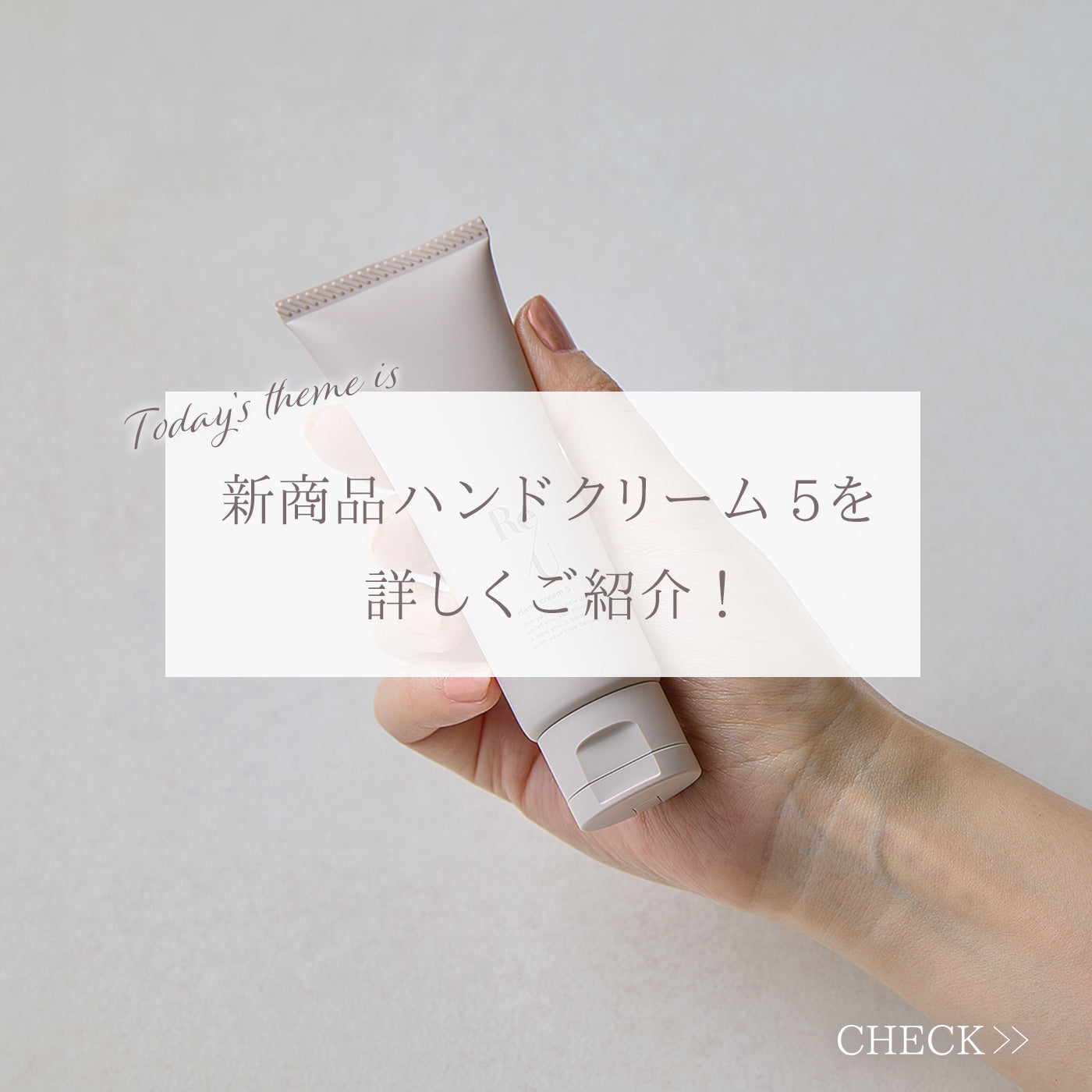みなさんは、骨盤底筋という筋肉群があることをご存じでしょうか?
「最近、下腹がぽっこりしてきた?」
「トイレが近くなった気がする。」
「なんだか姿勢が悪いかも」など。
これらの違和感を感じていたら、もしかしたらそれは「骨盤底筋からのサイン」かもしれません。大切なのは、今のうちに正しい知識を身につけて、適切にケアすること。
そこで注目したいのが「骨盤底筋群」。私たちの体を支え、健康を守るこの筋肉について、まずは基礎から学んでいきましょう。
今回はMTXスポーツ・関節クリニックの阿多由梨加院長に「骨盤底筋群の重要性」についてお話を伺いました。
骨盤底筋について
1. 骨盤底筋群とは
阿多院長:骨盤底筋群とは、尿道、膣、肛門にかけて内臓を支える筋肉の集まり。英語では「pelvic floor muscle」と呼ばれ、骨盤の“床”のような役割を果たしています。骨盤内には膀胱、子宮、直腸などの臓器が収まっており、骨盤底筋群がこれらの臓器を支えています。

2.骨盤底筋が支える3つの重要ポイント
阿多院長:次に、骨盤底筋の働きについて見ていきましょう。
①内臓を支えること
骨盤底筋群は、骨盤底に位置する子宮、膀胱、直腸などの臓器を支えながら、腹部や腰部の筋肉と連動し、胃や肝臓、小腸、大腸といった内臓の重みも支える重要な役割を担っています。特に妊娠中は、赤ちゃんや羊水、胎盤の重さが約5kgにもなるため、骨盤底筋群には普段以上に大きな負担がかかります。
②排尿や排便のコントロール
骨盤底筋群は、排尿や排便、おならのタイミングを調節する役割を果たします。尿を溜める際、膀胱周りの筋肉は水風船のように柔らかく伸び、逆に尿道の出口付近の筋肉がキュッと締まることで、尿が漏れないように調整されています。
骨盤底筋が緩み、バランスが崩れると、尿漏れなどのトラブルの原因となります。
③体幹を安定させること
体幹は、横隔膜(天井)、腹筋群(前の壁)、多裂筋(後ろの壁)、骨盤底筋(床)からなる「箱」のような構造によって支えられています。これらの筋肉が内側からバランスよく働くことで、安定した体幹が保たれます。特に骨盤底筋は「縁の下の力持ち」として、体をしっかりと支えているのです。
このように、骨盤底筋は私たちの体を支える重要な役割を果たしています。
では、あなたの骨盤底筋はしっかりと機能しているでしょうか?以下のチェック項目に当てはまるものがあるか、確認してみましょう。

チェックが多かった方は、骨盤底筋が弱くなり始めているサインかもしれません。
実は、骨盤底筋の機能が低下すると、体にはさまざまな影響が現れます。では、具体的にどんなトラブルが起こるのでしょうか?
骨盤底筋が弱る原因とトラブル
1.機能低下の原因
阿多院長:骨盤底筋の機能が低下する原因として、以下のような要因が挙げられます。
・出産などによって骨盤底筋群を傷める
・年齢を重ねるにつれて筋力が低下する
・更年期の女性ホルモン=エストロゲンの減少
エストロゲンは、筋肉や関節を保護し、膀胱や膣の働きをサポートするホルモン。
そのため、更年期になるとエストロゲンの分泌が減少し、骨盤底筋の機能が低下しやすくなるのです。
2.骨盤底筋の機能が低下しやすい人とは
阿多院長:皆さんは、どのような特徴や年齢の方が機能の低下を起こしやすいかご存知ですか?
・40歳から50歳前半の更年期世代
・妊娠および出産の経験がある方
・閉経した方
・インナーマッスルが弱く、運動習慣がない方
・トイレでいきむ癖がある方
・急に体重が増加した人
このような方々が挙げられます。
特に妊娠中は女性ホルモンが急激に上昇し、出産前後に急激に低下することが機能低下の原因とされています。また、更年期を迎えた女性は、女性ホルモンの急激な減少により骨盤底筋の機能が低下しやすくなります。
その他に、どのような影響があるか見てみましょう。

よく耳にする尿漏れの他にも、臓器脱や肩、腰に影響を及ぼすことがあるのです。
自己流のエクササイズを実践したり、骨盤底筋を意識して収縮させているつもりでも、エコーでチェックすると、お尻の筋肉に力を入れ過ぎて下から支えられず、逆に上から押し下げている方が多くいらっしゃいます。中には、無理な腹筋運動によって骨盤底筋を下げる原因を作ってしまう場合もあります。
セルフチェックだけでは不安な方や、すでにお困りの方は、ぜひMTXスポーツ・関節クリニックにご相談ください。

当院では、エコーを用いた診断で骨盤底筋の状態を正確にチェックし、一人ひとりに最適なトレーニング指導を行っています。
また、エコー検査の結果、骨盤底筋が原因ではなく、切迫性尿失禁・膀胱炎・神経異常の可能性が見つかることもあります。その場合は、薬の処方や泌尿器科への紹介も行っています。
尿漏れなどの症状がある方は、無理に我慢せず、一人で悩まずに、正しい知識を身につけ、一緒に解決方法を見つけていきましょう。気になる症状があれば、無理せず一度ご相談ください。
次回は理学療法士によるエコー診断やトレーニングの様子をご紹介するのでお見逃しなく。