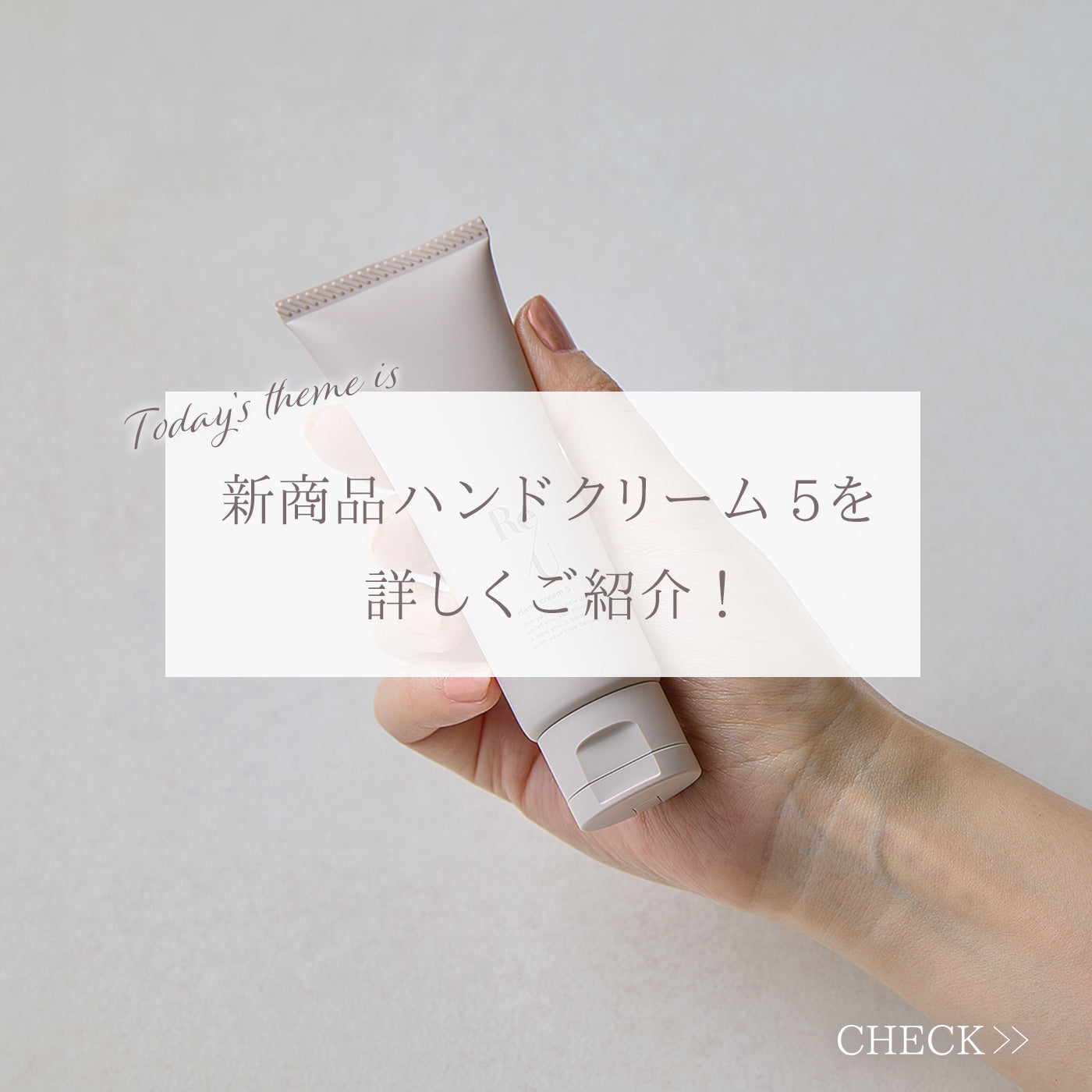皆さんは「腸」温めてますか?
夏に冷たい飲み物を飲みすぎたり、無意識にお腹を冷やしている方が多いのではないでしょうか。内臓、特に第二の脳と言われる腸が冷えると、悪影響を及ぼします。
今回は、なぜ腸を冷やすと良くないのか?温める方法や食材などご紹介します。
すぐに始められることばかりなので、ぜひ、チェックしてください。
■お腹が冷える原因は大きく2種類
お腹が冷える原因は「急性の冷え」と「慢性の冷え」の2種類あると考えられています。
急性の冷えは、下痢などの腹痛、冷えを感じる症状が現れ、一時的に回復するのが特徴です。しかし、慢性の冷えは長時間お腹が冷えている状態のこと。体質的、あるいは習慣的なものが原因です。
慢性の場合も下痢や腹痛なども現れますが、症状はいくつかあり、長期的に繰り返すことで回復しづらくなるのです。
腸を冷やすデメリット
お腹の冷え、特に腸が冷え続けるとどのようなデメリットがあるのでしょうか?
腸や内臓が冷えてしまうと、体は温度を保とうとして胃腸を必要以上に働かせます。その結果、胃腸が疲れやすくなり、消化の働きが弱まってしまいます。
さらに、冷えによって血流が悪くなり、胃腸に十分な血液が行き渡らなくなります。これにより、食べ物が消化しづらくなり、便秘や下痢、お腹にガスが溜まる、食欲不振などの悪循環に陥ります。
こうした悪循環から抜け出すには、どんなことに注意し、何をすればいいのでしょうか?

「腸温活」で免疫力アップ
身体の中でも消化吸収や排せつなど、大きな働きをする腸。冷えから守り、温めるのに効果的な方法は意外と簡単。季節を問わず、腹巻や湯たんぽ、最近では充電式カイロなどもあるので、身近な物から取り入れてみませんか?
また、物に頼らず自力で熱を作り出せるようになるために、下半身全体を使うスクワットをするのもおすすめ。朝晩数回からでもいいのでチャレンジしてみましょう。
食材選び
腸内環境を整えるためには食材選びも大切。腸内細菌のバランスを整え、負担をかけすぎない、消化しやすいものを取り入れることを意識しましょう。
ここからは、「腸活アドバイザー」の資格を持つブランドディレクター乙黒えり推薦の食材をご紹介します!

①主食編
さまざま穀物を含む雑穀米は、ミネラルが豊富と言われています。腸内の老廃物を排出し、腸内環境を整えることで便秘解消にも役立つと言われています。

さらに、コレステロールを下げ、肥満予防にも期待ができ、アンチエイジングのサポートもしてくれるのです。
白米に混ぜるだけで簡単に作れる雑穀米には特に、マグネシウム・カルシウム・鉄・カリウムなどが豊富で、ビタミンB1やビタミンB6は同じ量の白米と比較しても、約10倍以上のカルシウムや食物繊維を含むものもあります。
②野菜編
善玉菌を増やす食事をすることで腸内を弱酸性化させ、悪玉菌の増殖を抑制し、腸内環境を整えることができます。プロバイオティクスという善玉菌のエサとなる栄養分を含む食材を摂る必要がありますが、どんな野菜を摂り入れるといいのでしょうか?

ピックアップした野菜は、主に不溶性食物繊維と水溶性食物繊維の2つに分けられ、それぞれをバランス良く食べることで腸内環境に良い影響を与えます。
・不溶性食物繊維(さつまいも・かぼちゃ・れんこん等):水に溶けない性質で便のかさを増やし腸を刺激してくれます。その結果、便通を促し腸内の老廃物を排出するデトックス効果が期待できます。
※注意点※
摂り過ぎた場合、腸が過剰に刺激されることでガスが溜まり、腹部膨満感やお腹の張りを引き起こすことも。水分が不足していると便が硬くなり、逆に便秘になることもあるので、1日2リットル程度の水分をこまめに摂るようにしましょう。
・水溶性食物繊維(長芋・たまねぎ等):水に溶ける性質で腸内でゲル状になり、コレステロールや糖の吸収を抑える働きがあります。さらに、善玉菌のエサとなり腸内環境を整える役割をします。
※注意点※
摂り過ぎるとお腹がゆるくなり、下痢を引き起こすことがあります。特に水分と一緒に取らない場合、腸内で膨らみ過ぎて不快感を感じることもあるため、水分を取りながら、1日約5~6gを目安に摂取するよう心がけましょう。
③フルーツ
最後は食物繊維やビタミン、ミネラルを含むフルーツ。
摂り方によってはデメリットになることも。目的や注意点を詳しく見てみましょう。

・バナナ
1日あたりの適量:1本(約100~150g)
便秘解消におすすめのバナナは、常温保存するため腸を冷やしにくいフルーツ。
食物繊維やビタミンB6などを豊富に含むバナナは、素早いエネルギー補給にも適していますが、熟しすぎると糖分が多くなるため、過剰摂取には要注意。
・キウイ
1日あたりの適量:1~2個(約100~200g)
キウイの皮や果肉には水溶性食物繊維の一種ペクチンが含まれているため、腸内の善玉菌のエサとなり、腸内環境を整える効果があります。他にも疲労回復に関わる重要な成分であるクエン酸も含みます。
冷え性の方はホットスムージーやヨーグルトに加えるなど、ひと手間加えて摂ると◎。
・りんご
1日あたりの適量: 1個の半分~1個(約150~200g)
胃腸にやさしいりんごは、腸内細菌にアプローチして活性化させるという研究も出ているほど有能で、水溶性食物繊維であるペクチンも含むため、腸内細菌のエサとなり、免疫機能や便通改善などもサポート。皮部分にポリフェノールが多く含まれるため、よく洗い皮付きで食べるといいでしょう。
おすすめの食べ方は、蒸したり焼いて食べるといいそうです。
実は簡単に始められる腸温活。冷え性でお悩みの方は、ぜひお試しください。